浦添城趾にある伊波普猷のお墓参りをして手を合わせてきました。
お墓入り口の右手には顕彰碑が建てられ、前方は庭園となっています。
とても静かな、落ちついた雰囲気がする場所でした。


浦添城趾にある伊波普猷のお墓参りをして手を合わせてきました。
お墓入り口の右手には顕彰碑が建てられ、前方は庭園となっています。
とても静かな、落ちついた雰囲気がする場所でした。


まだ肌寒いですが、季節は春となりました。
桜の花があちこちで咲いており、目を楽しませてくれます。

比嘉春潮全集2巻に収録されている「沖縄の明治百年」は興味深い随筆です。これの原典にあたってみたくなって探していました。
ところが全集で『琉球新報』1968年1月1日に掲載とされていましたが見つかりません。調べた結果、『琉球新報』1967年1月21日(土)8面が正しい日付であることがわかりました。
「沖縄の明治百年」は、当時の子どもの学校生活がどのようなものだったのかをうかがい知ることができる面白い文章だと思います。明治の当時、日常語は沖縄口が優勢だったので「内地語」への順応がかなり難しかったようです。
私など右(みぎ)は水(みぢ)のことと決めてしまい、先生の「右向け右」の号令に、水のある田んぼの方に威勢よく向かって笑われたこともあった。
大事なところは、比嘉が「右」を「水」と間違えたことではなく、「威勢よく」というくだりです。他の子が皆右を向いているのに、左が正しいと考えた比嘉は自分の判断に自信を持って「得々と」主張している様子がうかがえます。学校では群を抜いて優秀だったという比嘉らしい行動ですね。
比嘉の口述筆記による自叙伝『沖縄の歳月 自伝的回想から』(中公新書、1969年)なども当時の沖縄の世相を知る上で重要な文献といえます。
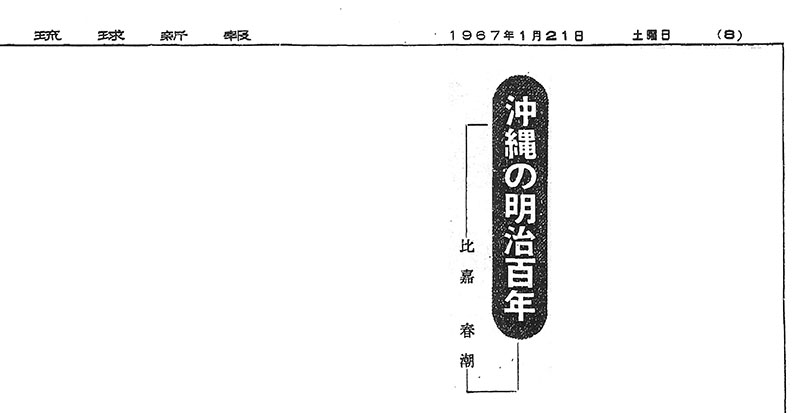
大雪となりました。
しばらく寒さが続きそうです。

今日は晴れて清々しい一日となりました。
立山連峰の眺めも素晴らしかったです。

今日は1月14日の日曜日、大学入学共通テストの2日目になります。
晴れてはいますが相当寒い朝になりました。
現在午前7時30分くらいですが、気象サイトではマイナス3.4℃と表示されています。道路がガチガチに凍っています。


新しい年を迎えました。本年もよろしくお願いいたします。
皆様にとって充実した一年となりますよう、心よりお祈りいたします。



沖縄滞在3日目になりました。時間がたつのが早いです。
富山に比べると気温が高いけど、肌寒い感じです。
机の引き出しをあけてみると、なんと金武中学校の帽章が出てきました。確か1948年の新制中学発足当時のものから一度改められたもので、二代目になると思います。懐かしいです。

伊波普猷の生家跡地に行ってみました。明治の当時はどんな街並みだったのでしょうか。


14時半に小松空港を出発し、17時ちょうどくらいに那覇空港到着。機内で寝れたので移動の疲れから復活しました。今日はきょうだいが集まって那覇で忘年会。
伊波普猷の生家跡地に少しだけ立ち寄ってみました。那覇市歴史博物館Webサイトで確認したのがきっかけ。宿泊先から歩いて行けます。
場所は那覇市西1-13-3、伊波の写真と経歴が記されたパネルが設置されています(1997年8月に設置されたとのこと)。現在の沖縄県立図書館のすぐ近くなので感慨深いです。伊波は初代沖縄県立図書館長をつとめた人物なのだから。
もう薄暗い時間になっていたので、明日朝もう一度行って写真を撮ろうと思います。


